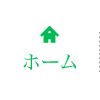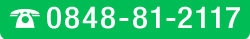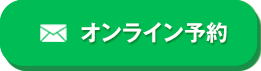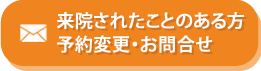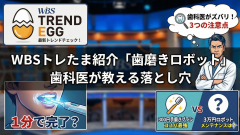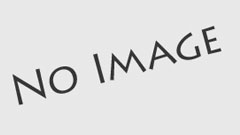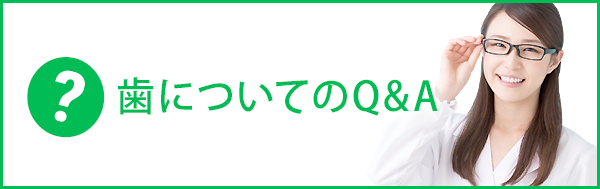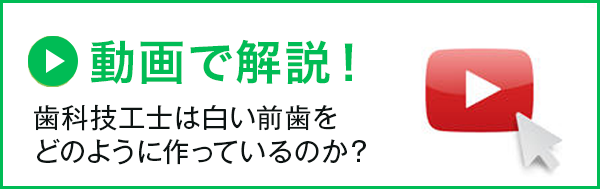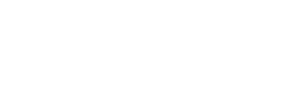最近の子どもの歯ならびが悪くなった本当の理由
🦷 最近の子どもの歯ならびに起きていること
最近、歯科医院でお子さんのお口を診ると、ある共通点に気づきます。
たとえば下の前歯4本分のスペースに、わずか3本の永久歯が窮屈そうに並び、上の前歯も2本だけしか生えてこない。残りの歯が出る場所が「もう残っていない」ように見えるケースがとても増えています。
昔に比べて、子どもの歯ならびが乱れている―。
その理由としてよく挙げられるのが「硬いものを噛まなくなった」「顎が小さくなった」という説明です。
しかし、最新の研究では、それだけでは説明できない“もう一つの真実”が見えてきています。
🍽 食生活の変化がつくる「小顔」と「大きな歯」
50年前と比べ、私たちの生活は大きく変わりました。
食事の欧米化が進み、柔らかく高カロリー・高タンパクな食事が中心になりました。
この結果、噛む回数(咀嚼運動)が大幅に減少しています。
引用された専門書によると、
「若者の身長は10cm近く伸び、体格は大きくなったのに対し、顎の骨は十分に発達していない。」
「エラの張りが小さくなり、顔の奥行きと横幅が狭くなった結果、面長で小顔の顔つきが増えた。」
つまり、体は大きくなったのに顎は小さく、歯は大きくなったため、歯が並ぶスペースが足りなくなっているのです。
これこそが「最近の子どもの歯ならびが悪くなっている最大の理由」といえるでしょう。
👶 マイナス1歳から始まる「歯育」と「食育」
子どもの歯ならびは、生まれる前から準備が始まっています。
妊娠期からの栄養バランスが、顎や歯の大きさの基礎をつくるからです。
理想的な食育とは、昔ながらの日本食にヒントがあります。
皮ごとのお米やお芋 よく噛む根菜類 魚介類や鶏卵を適度に取り入れる こうした**「かむ力を育てる食事」**が、子どもの歯並びと顎の発達にとって最良のトレーニングです。
🌸 三原市から発信する“次世代の歯育て”
ここ三原市でも、昔ながらの和食文化を子どもたちに伝える取り組みが増えています。
地域全体で「よく噛む・味わう・ゆっくり食べる」ことを意識できれば、次の世代の歯ならびは確実に変わっていくでしょう。
未来の子どもの笑顔と健康のために。
歯育ては“マイナス1歳”から始まる一生のプレゼントです。
Author Profile
- 大名 幸一 Koichi Omyo
Latest entries
この記事をFacebookでシェアする