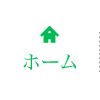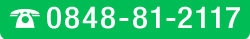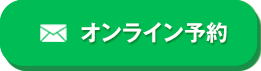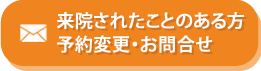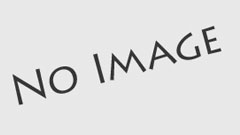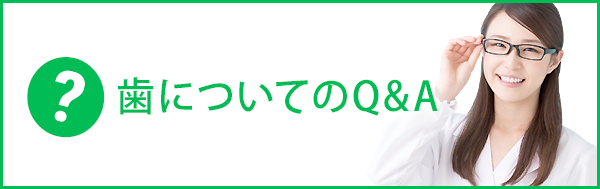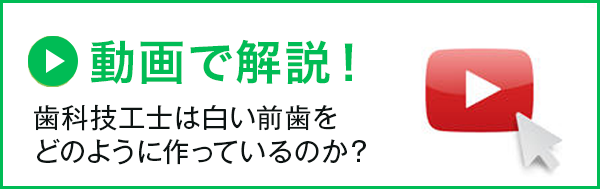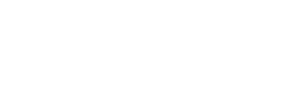カロリーの嘘?胃腸は燃えていない|歯科医が語る栄養学の非常識
「カロリー」とは、食べ物を酸素で燃やした時に発生する熱量のことです。
学生の頃に一度は習いましたよね。つまり、カロリーとは「燃やしたときの発熱エネルギー」の単位。厚生労働省が定める「1日の摂取カロリー」も、この燃焼実験を基準にしています。
この“カロリーの足し算”が、現代栄養学の根本を支えてきました。
しかし、ここに大きな誤解があります。
食べ物は胃腸で燃えていない
ちょっと考えてみてください。
食べ物って、胃や腸の中で燃えていますか? 火がついて、燃え上がって、灰になっているわけではありませんよね。
実際のところ、私たちの体の中では「燃焼」ではなく、化学反応(代謝)によってエネルギーを生み出しています。
つまり、「カロリー=燃やした熱量」という考え方は、人体にはそのまま当てはまらないのです。
カロリー計算の落とし穴
- 燃焼実験で得たカロリーと、体が実際に吸収・利用できるエネルギーは違う
- 同じ100kcalでも、自然食品と加工食品では吸収率が異なる
- 「カロリーゼロ飲料」も、代謝や腸内環境に影響を及ぼす可能性がある
つまり、「カロリーの足し算」だけでは健康を説明できない時代に入っているのです。
歯科医が見た「カロリー信仰」の危険性
歯科の現場では、「低カロリー志向」が思わぬ弊害を生んでいます。
やわらかい・飲み込みやすい食品ばかりを選ぶことで、次のような症状が増えています。
- 咀嚼回数の減少
- 唾液分泌の低下
- 虫歯・歯周病・口臭リスクの上昇
「燃やす」よりも、「噛む・消化・吸収」の質を高めることが、真の健康につながります。
まとめ:体はストーブではない
- カロリーは「燃やした熱量」であり、「体で使うエネルギー」ではない
- 胃腸は燃焼装置ではなく、化学反応の場である
- 健康を左右するのは、カロリーよりも“食べ方”と“質”
関連記事はこちら
「カロリー」という数字よりも、「食材の質」と「噛む回数」を意識してみましょう。
それこそが、体と歯を健康に保つ最良の“エネルギー管理”です。
監修:大名歯科(広島県三原市)
歯科医師:大明 康一(おおみょう こういち)
https://www.ohmyo.com/