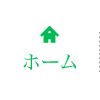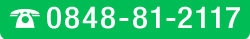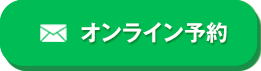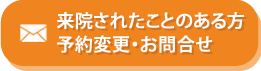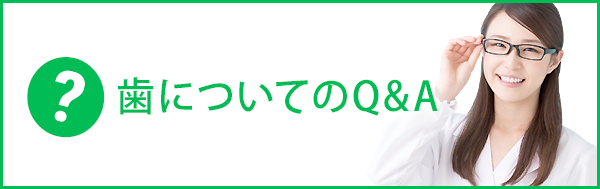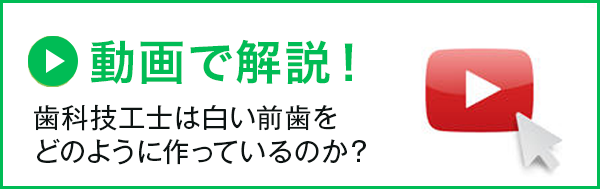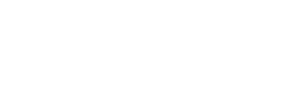歯磨き粉も“薬”?知らないと危険な、毎日の“無意識の服薬習慣”
「薬は飲むほど健康を奪う?」歯科医が語る“本当に続けていい薬”とは
のみ続けてはいけない薬、のみ続けてもいい薬はあるのか?
健康診断の数値を早く改善したい──その気持ちは誰でも同じです。
しかし、副作用のない薬は存在しません。
どんな薬も「症状を抑える代わりに、別の負担を体にかけている」という現実があります。
気付けば薬がどんどん増えていく…。
そんな経験はありませんか?
- 空腹を早く満たしたくて加工食品を食べる
- 生活習慣が乱れ、慢性疾患になる
- 検査数値を下げたくて薬を飲む
- 副作用が出て、薬がさらに増える
──この“負のループ”こそ、現代医療の落とし穴です。
「〇〇に効く薬」の副作用が同じ〇〇…?
たとえば、抗うつ薬のひとつであるパキシル。
薬効には「憂うつな気分を和らげ、意欲などを改善する」と書かれていますが、副作用の欄には、
- めまい
- 頭痛
- 譫妄(意識がはっきりしない状態)
- 倦怠・倦怠感
といった症状が並びます。
これでは、かえって憂うつが強くなってしまう方もいるかもしれません。
薬を飲む前こそ、「副作用」をしつこいほど確認する必要があります。
知らない間に“毎日薬を飲んでいる”人が多いという事実
実は、歯科の世界にも「毎日薬を続けている人」がたくさんいます。
それが、歯磨き粉とデンタルリンスです。
歯磨き粉・デンタルリンスは“薬”です
毎日毎日、しかも一日三回、歯磨き粉をたっぷりつけて歯を磨く。
寝る前にはデンタルリンスを欠かさない。
そんな方は少なくありません。
しかし、歯磨き粉もデンタルリンスも「薬」に分類されるものです。
高血圧や糖尿病の薬と同じく、「いつまで続けるのか」「なぜ使い始めたのか」を本当は考える必要があります。
簡単に言うと、歯磨き粉やデンタルリンスの中には、自然界に存在しない成分が多く含まれています。
自然ではない成分なので、確かに口の中の菌は減るかもしれません。
しかし、口の中の菌はゼロにはならず、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れてしまいます。
このバランスの崩れこそが、歯周病の進行を手助けしてしまう要因にもなり得るのです。
粘膜は「経皮毒」を吸収しやすい入口
また、角化層が厚い皮膚に触れるソープ(石油化学洗剤)と違って、口の中は粘膜です。
粘膜は吸収力が高いため、「経皮毒」の観点から見ても、口の中に化学物質を入れることはリスクが高いと考えられます。
重度歯周病には一時的に“あり”、それ以外は“不要”かもしれません
重度歯周病で口の中がバイ菌だらけの方は、一時的に菌全体を減らす意味で、薬用の歯磨き粉やデンタルリンスを使う選択は「あり」かもしれません。
しかし、歯周病が中程度以下の一般的な方が、
- 副作用が必ずある洗剤成分を
- 吸収率の高い口の中で
- 長期間、継続的に使用し続ける
というのは、将来の健康リスクを自ら上げていると言わざるを得ません。
歯科医としての実体験:10年以上、歯磨き粉もリンスも使っていません
私は歯科医ですが、10年以上、歯磨き粉を使用していません。
デンタルリンスも、職業上の確認のために数回使用した程度です。
それでも、歯周病を含め、特に問題は生じていません。
なぜかというと、本当に歯周病にならないための予防は、歯磨き粉ではない別のところにあるからです。
(その具体的な方法については、別の記事で詳しくご紹介します)
薬を飲む前に。歯磨き粉を買う前に。「本当に必要か?」を確認しましょう
薬は便利ですが、その裏側には必ずリスクがあります。
歯磨き粉やデンタルリンスも同じです。
健康を守るために大切なのは、
- 「安心そうだから」なんとなく続ける
- 「みんな使っているから」と疑わず使う
- 「CMで良さそうだから」と深く考えずに買う
ことではありません。
「自分の身体に本当に必要かどうか」を、しつこいくらい確認すること。
それこそが、健康寿命を延ばし、不要な薬・不要な習慣から身体を守る、いちばん確実な方法です。
薬は服用する前に、歯磨き粉やデンタルリンスは毎日使い続ける前に、「本当に必要か?」を一度立ち止まって考えてみましょう。
Author Profile
- 大名 幸一 Koichi Omyo
Latest entries
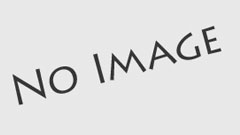 広島県三原市2025.12.29大名歯科ってどんな歯科医院ですか?とAIにきいてみると
広島県三原市2025.12.29大名歯科ってどんな歯科医院ですか?とAIにきいてみると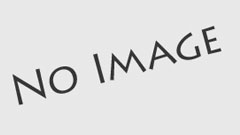 歯科2025.12.28歯医者が休みの時ほど歯が痛む理由、知っていますか?
歯科2025.12.28歯医者が休みの時ほど歯が痛む理由、知っていますか?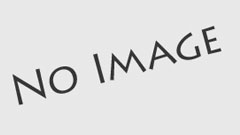 咬み合わせ2025.12.27歯ぎしり・噛みしめが歯を壊す?ストレスと歯の深い関係
咬み合わせ2025.12.27歯ぎしり・噛みしめが歯を壊す?ストレスと歯の深い関係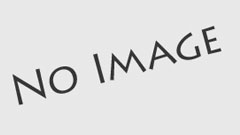 虫歯2025.12.26虫歯予防に歯みがきは効果ない?歯科医が教える本当の予防法
虫歯2025.12.26虫歯予防に歯みがきは効果ない?歯科医が教える本当の予防法
この記事をFacebookでシェアする