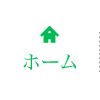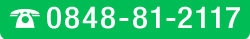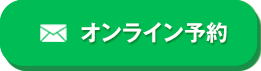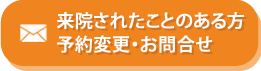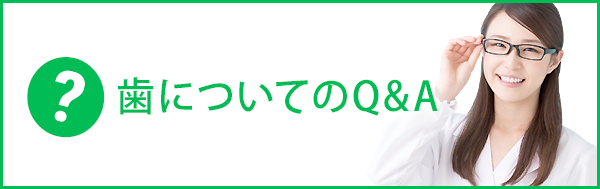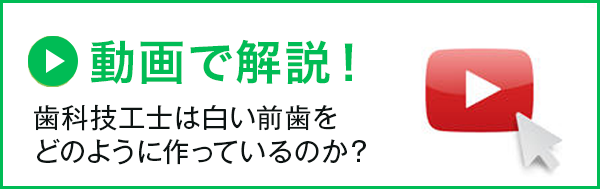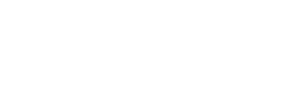口呼吸は万病のもと!子どもの唇荒れ・虫歯・いびきの正体を歯科医が解説
口呼吸は万病のもと!子どもの唇荒れ・虫歯・いびきの正体を歯科医が解説
口呼吸が増えている?
最近、唇が荒れている幼児や小学生がとても増えています。とくに秋から冬にかけては空気が乾燥し、口呼吸の子どもにとってつらい季節です。
リップクリームを塗ると一時的には改善したように見えますが、これはあくまで対症療法にすぎません。
「ずっと塗り続けていい薬」など存在せず、問題の根本は口呼吸そのものにあります。
口呼吸が引き起こすトラブル
1. 唾液が蒸発して虫歯・歯周病のリスクアップ
口呼吸では、口の中が常に乾燥し、唾液がすぐに蒸発してしまいます。唾液には次のような大切な働きがあります。
- 抗菌作用(細菌の増殖を抑える)
- 酸の中和作用(虫歯の原因となる酸を中和する)
- 歯の再石灰化(溶けかけた歯を修復する)
この自浄作用が失われることで、虫歯や歯周病が急速に進行しやすい環境になってしまいます。
2. 風邪・インフルエンザにかかりやすくなる
本来、鼻にはつぎのような重要なフィルター機能があります。
- 空気を加湿して、のどを守る
- 空気を適度な温度に調整する
- ウイルスやホコリ、花粉などをキャッチして体内に入る量を減らす
しかし、口呼吸では鼻の防御システムを素通りしてしまうため、
ウイルスや細菌が直接のど(咽頭)や気管に届きやすくなり、風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。
3. 歯ならび・顎の発育に悪影響
成長期の子どもが長期間口呼吸をしていると、歯列や顎の発育にも大きな影響が出ます。
- 上顎が狭くなる
- 歯がきれいに並ばない
- 出っ歯になりやすい
- 受け口傾向になる
このように歯列不正や顎骨の発育不足につながるため、歯科医として最も見逃したくないポイントの一つです。
とくに注意が必要なのは「就寝中の口呼吸」
寝ている間はもともと唾液の分泌量が少なくなります。
その状態で口呼吸が続くと、口の中は完全にカラカラの乾燥状態になり、虫歯や歯周病のリスクが昼間の何倍にも跳ね上がります。
「朝起きたときに口が渇いている」「口臭が気になる」という方は、就寝中の口呼吸をしているサインかもしれません。
口呼吸への対策方法
1. 鼻が詰まりやすい場合は「鼻」の治療から
両鼻が同時に完全に詰まることは稀ですが、鼻炎・アレルギー・扁桃肥大などが疑われる場合は、歯科だけでなく次のような診療科に相談が必要なケースもあります。
- 耳鼻科
- 小児科
- アレルギー科
鼻の通りが悪いままでは、いくら口を閉じようと思っても長続きしません。
まずは鼻でしっかり呼吸できる状態をつくることが、口呼吸改善の第一歩です。
2. 自力でできる口呼吸対策
鼻の通りが大きな問題でない場合、多くは生活習慣やクセの見直しで改善が期待できます。
就寝中のマスク
就寝時にマスクをつけると、
- 適度な加湿効果で口の乾燥を防ぎやすい
- 自然と口が閉じやすくなる
といったメリットがあります。マスクに慣れているお子さんには、比較的取り入れやすい方法です。
サージカルテープを口唇に縦一本
マスクが苦手な方には、剥がしやすいサージカルテープを唇に縦に一本貼って寝る方法も効果的です。
口をしっかり密閉するのではなく、軽く閉じる程度にしておくことで、
- 安全性を保ちながら口呼吸のクセを減らす
- 「口を閉じて寝る」習慣づけのサポートになる
といったメリットがあります。
粘着力が強すぎないテープを選ぶことがポイントです。
まとめ:口呼吸は「ただのクセ」ではありません
口呼吸は単なるクセではなく、
虫歯・歯周病・風邪・インフルエンザ・歯ならび・顎の発育など、全身の健康に関わる生活習慣病の一つと考えるべきです。
お子さんの唇がいつも荒れている、口をポカンと開けている、いびきをかく、といった様子が見られたら、それは体からのサインかもしれません。
早めに対策をすることで、将来の歯ならびや全身の健康リスクを大きく減らすことができます。
大名歯科では、口呼吸や鼻づまり、歯列への影響なども含めて、お口全体と全身の健康を見据えたアドバイスを行っています。
気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。
Author Profile
- 大名 幸一 Koichi Omyo
Latest entries
 健康2026.02.26【0円健康法】食品添加物や食中毒が不安な方へ。お金も時間もかけない最強の対策
健康2026.02.26【0円健康法】食品添加物や食中毒が不安な方へ。お金も時間もかけない最強の対策 健康2026.02.25【歯科医が解説】朝起きると喉がカラカラ・唇ガサガサ…加湿器より効果的な「根本解決法」とは?
健康2026.02.25【歯科医が解説】朝起きると喉がカラカラ・唇ガサガサ…加湿器より効果的な「根本解決法」とは?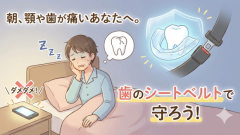 咬み合わせ2026.02.24朝起きると顎や歯が痛い?「無意識の食いしばり」を防ぐ2つの習慣
咬み合わせ2026.02.24朝起きると顎や歯が痛い?「無意識の食いしばり」を防ぐ2つの習慣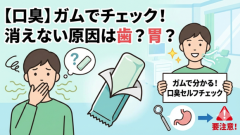 予防歯科2026.02.23【口臭セルフチェック】ガムを噛んでも臭いが消えない原因と隠れた病気
予防歯科2026.02.23【口臭セルフチェック】ガムを噛んでも臭いが消えない原因と隠れた病気
この記事をFacebookでシェアする